リッチになるために読むべき本:Daniel Kahneman「Thinking, Fast and Slow」
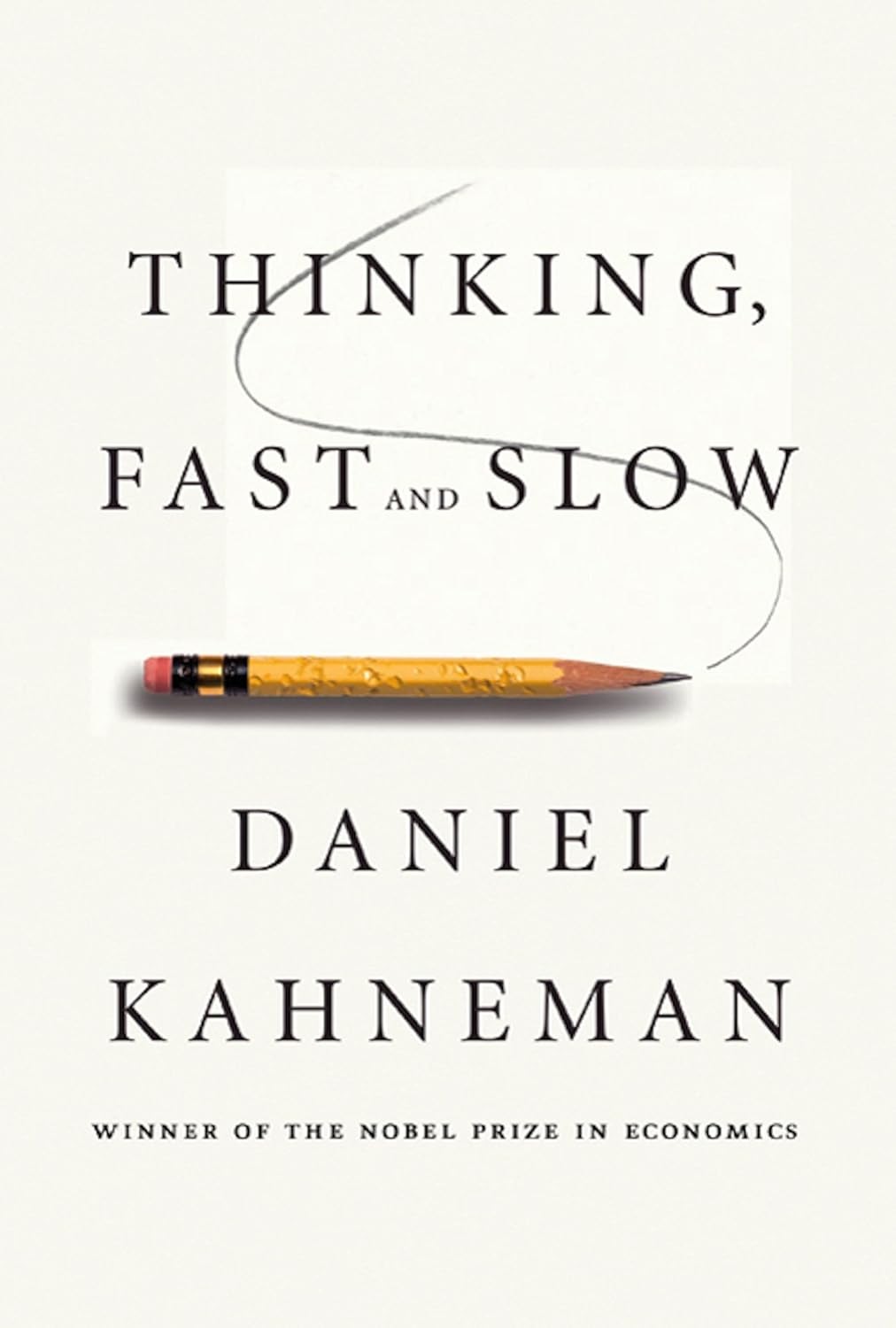
本書のエッセンス:30
-
人間の思考には、直感的で速い「システム1」と、理性的で遅い「システム2」の2種類が存在する。富を築く意思決定には、両者の特性の理解が不可欠である。
-
システム2は基本的に怠け者であり、意識的に使わない限り、私たちはシステム1の直感的な判断に流されてしまう。重要な判断の前には一息つき、システム2を起動させる必要がある。
-
最初に提示された価格や数値(アンカー)は、その後の判断を不合理に歪める。交渉や投資において、相手が提示した数字に惑わされず、自分自身の基準を持つことが重要。
-
人は思い出しやすい出来事(利用可能性)の確率を過大評価する。メディアが報じる華々しい成功事例や悲惨な破産物語に惑わされず、客観的なデータに基づいて判断すべき。
-
魅力的な事業計画が、統計的に成功確率が高いとは限らない。人はステレオタイプ(代表性)に合致するストーリーを信じやすいが、現実はもっと複雑である。
-
少数の成功例や失敗例から、市場全体の法則を導き出すのは危険だ(少数の法則)。十分なデータに基づかない判断はギャンブルに等しい。
-
もっともらしい成功物語(原因)よりも、客観的な統計データを重視すべきである。成功者の語るストーリーは、後付けのバイアスに満ちていることを忘れてはならない。
-
驚異的なパフォーマンスは、実力だけでなく幸運の産物であることが多い。極端な結果の次には、より平均的な結果が出やすい(平均への回帰)と心得るべきだ。
-
過去を振り返るとすべてが必然であったかのように思えるが、それは「理解の錯覚」にすぎない。この後知恵バイアスを自覚し、未来を予測できるという過信を捨てることだ。
-
自分の判断の正しさを過信するな(妥当性の錯覚)。特に専門分野で自信があるときほど、自分の直感を疑い、客観的な証拠を探す姿勢が富を遠ざけない。
-
投資判断などの予測においては、専門家の直感よりも、客観的なデータに基づいた単純な数式(アルゴリズム)の方が信頼できることが多い。
-
専門家の直感を信じるべきなのは、その分野が予測可能な規則性を持ち、かつその専門家が十分な練習と迅速なフィードバックを得てきた場合に限られる。
-
計画を立てる際は、自分の計画(内部の視点)がいかに完璧に見えても、類似ケースの統計データ(外部の視点)を参照し、計画の錯誤を避けることが賢明だ。
-
楽観主義は行動の原動力だが、過剰な楽観は破滅を招く。競争相手の存在や不運といったネガティブな情報を無視する傾向(競争の無視)に注意が必要だ。
-
重要な意思決定の前には「プレモルテム」を実施する。計画が1年後に大失敗したと仮定し、その原因を事前に考えることで、隠れたリスクを洗い出すことができる。
-
人は富の絶対量ではなく、現状(参照点)からの変化、すなわち「利得」と「損失」で価値を判断する。これがプロスペクト理論の核心である。
-
損失の痛みは、同額の利得の喜びの約2倍大きく感じる(損失回避)。この心理が、損失を確定させることをためらわせ、より大きな失敗を招く原因となる。
-
一度手にしたものを、手に入れる前より高く評価してしまう(保有効果)。これにより、不要な資産や不採算事業を合理的に手放すことが困難になる。
-
人は確実な利益の前ではリスクを避け(リスク回避)、確実な損失の前ではリスクを取る(リスク追求)傾向がある。この心理を理解し、冷静に判断することが求められる。
-
確率が極めて低い案件(宝くじやハイリスク投資)の価値を過大評価し、逆に確率が極めて高い案件の価値を過小評価する傾向を知り、冷静な確率判断を心掛ける。
-
同じ内容でも、その表現方法(フレーミング)によって意思決定は大きく変わる。「コスト」と表現されるか「損失」と表現されるかで、あなたの判断は操作されうる。
-
人は心の中でお金を色分けし(メンタル・アカウンティング)、使途によって価値判断を変えてしまう。しかし、お金はお金であり、その非合理性が富の形成を妨げる。
-
「これだけ投資したのだから」という考えはサンクコストの錯誤である。過去の投資額に囚われず、これからの見込みだけで将来の判断を下すべきだ。
-
行動したことによる失敗は、行動しなかったことによる失敗よりも強い後悔(リグレット)を生む。この感情を恐れるあまり、好機を逃してはならない。
-
私たちの意思決定は「記憶する自己」によって支配される。しかし、良い記憶が必ずしも良い経験の総和と一致するわけではないことを知るべきだ。
-
経験の快苦は、その長さ(持続時間)ではなく、最も感情が昂った瞬間(ピーク)と最後の瞬間(エンド)の記憶で評価される。短期的な利益に惑わされてはならない。
-
人は自分の人生を一つの物語として捉え、良い結末を求める。この物語への欲求が、損失の確定を遅らせるなど、非合理的な経済判断を後押しすることがある。
-
幸福には「経験する自己」が感じる幸福と、「記憶する自己」が評価する人生の満足度の2種類がある。金銭的な成功は後者を高めるが、前者を必ずしも高めるとは限らない。
-
特定の事柄について考えているとき、その重要性を過大評価してしまう(フォーカシング・イリュージョン)。家や車を買っても、それがもたらす幸福への影響は限定的だ。
-
自分の直感を鵜呑みにせず、判断の誤りを引き起こす心理的バイアスを理解し、意識的にシステム2を働かせること。これこそが、より豊かになるための賢明な意思決定への道である。









